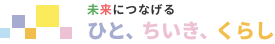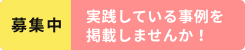「医療と福祉との橋渡し」を実現した名古屋ライトハウス
視覚障がい者の福祉向上をめざし、ニューヨークから世界に広がった「ライトハウス(灯台)運動」。後に日本にも波及したこのムーブメントを出発点とするのが、愛知県名古屋市の社会福祉法人名古屋ライトハウスです。
身体・知的・精神の各障がいがある方がたに加え、高齢者も支援の対象とし、8つの拠点で46の事業を展開しています。目の前にいる当事者をひたむきに支援する、という意味で「ひとりの幸せのために」を掲げ、まもなく法人創立80周年を迎えます。
地域の福祉向上のため、公益事業も積極的に展開してきましたが、なかでも法人を特徴づけているのが医療との連携です。法人の運営する「情報文化センター」と「視覚総合相談室」が複数の総合病院に出張し、視覚に関する福祉相談ブースを設けています。これは近県でもあまり例のない、革新的な取組です。
出張相談が実現すると、これまで課題だった医療と福祉とのあいだの空白がなくなるような大きな手応えが得られました。一つには、退院とともに途絶えていた情報を継続的に届けられるようになったこと。二つ目に、一人ひとりの病状や段階に合ったタイミングで情報提供できるようになったこと。三つ目に、障がい受け入れて新たな人生を歩むという困難な作業に、ピアサポーターとして寄り添えるようになったことです。


情報の断絶を防ぐ
名古屋ライトハウスの挑戦が始まる前、医療と福祉との連携は必ずしもスムーズではありませんでした。視覚障がいには先天性のもののほか、成人後に事故や病気で視力を失うケースも多くあります。見えにくさを抱える人が最初に訪れるのは医療機関ですが、その先につながらないことが課題でした。
山下文明専務理事は「私どもの周知不足なのですが、これまでは治療が終わって退院すると情報が途絶えていたのです。」と自戒を込めて話します。行政機関などでも情報提供は行いますが、一人ひとりのニーズに合わせたきめ細やかな紹介にはなりにくいものでした。
「どうすればいいのか、どこに電話すれば相談できるのかもわからない。点字を覚えることも、歩行訓練も受けることもなく、数か月どころか数十年も閉じこもっていたという人もいました。」と山下専務理事は振り返ります。
病院内に相談ブースがあることで、当事者は入院中や通院のついでなど、自然に相談に立ち寄ることができます。病気の進行に応じて必要な情報を提供できるので、時機を逸することがありません。病院内でも認知度が高まり、医療ソーシャルワーカーが退院患者を相談機関につないでくれるなど、副次的な効果も期待できます。
対象者が相談に訪れるのを待つ姿勢ではなく、対象者がいる病院に自らアプローチしたことにこの事業の意義があります。「私たちの支援の対象者は、まずは病院にいる。病院と問題意識や課題、情報を共有することは当事者にとっても有益だろうと信じています」と山下専務理事は語ります。


一人ひとりのタイミングで
視覚障がいの程度や、病気の進行状況は一人ひとり異なります。必要となる情報も刻々と変化していきます。「相談室では自らも視覚障がいがある当事者職員が親身になって、寄り添って話を聞きます。こういう選択肢があるよ、それにはこういうメリットがあるよ、こういうデメリットがあるよ、という情報を、その人に必要なタイミングで提供できるのです」と山下専務理事は話します。
職員は障害者総合支援法に基づく相談支援専門員も兼ねており、相談内容によって相談支援事業にシームレスに移行できます。「ピア的な立場で相談を受けながら、より専門的な知識と情報が必要なケースでも専門性を担保しながら対応できます」と山下専務理事はメリットを語ります。
名古屋ライトハウスの運営する「情報文化センター」は点字の専門機関であるほか、白杖の使い方を指導する歩行訓練士の斡旋なども行えます。また、法人では歴史的に「生活に耐えうる高工賃の仕事」の提供と「安心できる住まい」の確保を重視してきました。「どんな仕事でも働くことは社会の中での役割ですし、機能ですし、誇りです。そこはとても大切にしてきました。」という山下専務理事の言葉のとおり、就労継続支援事業所も複数運営しています。


心理的な壁を越えて
実は病院内で視覚障がいの情報を周知するのは簡単なことではありませんでした。事故や病気による中途障がい者にとって大きな壁が、障がい受容のプロセスです。当事者の心情を考え、病院内で「全盲」や「視覚障がい」という言葉をあえて出さなかった時代もあると山下専務理事は話します。当事者自身も職を失うことなどを恐れて症状を隠し、そのうちに病気が進行していく例もありました。とりわけ全盲であることは、認めにくいものでした。山下専務理事は「そこを飛び越えて、障がいを受容しながら必要な情報や知識を得ることがとても大切だと思ったのです」と力を込めます。
病院の外でも事情は同じです。山下専務理事は「自分からは決して言わないけれど、障害者手帳をもっていない弱視の方は、正確には何人いるかわからないぐらい実は地域にいらっしゃるんです」と話します。
相談室には、全盲の当事者職員を中心に年間300件ほどの電話相談や来所相談を受けてきた実績があります。ケースワークの視点をもちながら、共感的姿勢で初期の段階から関わることは、視覚障がい者の生活再建や再出発の大きな助けとなります。とりわけ障がい受容の観点では、当事者職員がピアカウンセラーとして気持ちの整理を手伝えることが強みです。


地域とつながる「視覚総合相談室」
本体となる「視覚総合相談室」の誕生は、平成28年にさかのぼります。創立70周年を記念して新規事業のアイディアを内外から募った「名古屋ライトハウスの未来像を考えよう」コンテストで、60件を超える応募のなかから選ばれたのが、視覚障がい者を総合的にサポートできるワンストップセンターの構想でした。
それ以前から名古屋ライトハウスでは点字図書館の機能をもつ「情報文化センター」を運営していましたが、「地域社会にも困っている人がいるのではないか」「よりインフォーマルな相談窓口が必要ではないか」という職員からの提案を具体化したのが視覚総合相談室です。
相談室は地下鉄駅から連絡通路で直接アクセスできる交通至便な場所にあります。山下専務理事が「何でも相談」と表現するとおり、相談内容は教育相談、生活相談、心の悩み、福祉サービスの問い合わせなど多岐にわたります。障害者手帳がなくても相談でき、加齢によって視力が衰えてきた高齢者や、読み書きの障がいであるディスレクシア当事者も対象です。
法人には当事者職員もいることから、教育と福祉、医療と福祉の連携不足には強い実感がありました。眼科医との個人的なつながりのほか、地域の眼科医会の会合などを通じて横の連携を強め、名古屋市立大学病院をはじめとする3か所の総合病院で相談ブースの開設が叶ったのです。
スタートから4年が経過した医療機関での出張相談は、今年度から名古屋市の委託事業となりました。開始当初は財源の保証のない自主事業でしたが、「それはもう、法人理念である、一人の視覚障がい者のためだけです」と山下専務理事は明言します。
現在、発症や受傷直後から相談できる視覚総合相談室は、視力の低下に戸惑う人にとって水先案内人の役割を担っています。視力を失うという大変な混乱のなか、取り残される人が出ないよう尽力するのが視覚総合相談室の大きな使命となっています。


10年後も存在し続けるために
昭和21年に前身となる「愛盲ホーム光和寮」を開設した名古屋ライトハウスは、来年80周年を迎えます。次の10年に向け、若い職員を中心に法人の未来を考える「未来プロジェクト(仮称)」の準備を進めています。夢を自由に表現した70周年の「名古屋ライトハウスの未来像を考えよう」コンテストに比べ、より現実的で実践的なプロジェクトです。
新型コロナウイルス流行という社会的危機は、法人の在り方を深く見直す機会となりました。山下専務理事は柔軟な発想を大切にする一方で、収支を含めた事業の持続性についてもシビアに捉えています。「10年後も同じようにこの施設がある、このサービスが継続しているという安心感は、障がい当事者にとって大きな意味がある」と話します。「そのためには地域のニーズを一生懸命汲んで、地域にとってかけがえのない、絶対になくてはならない位置に立つこと」──そう決意を新たにしています。


施設概要

- 法人名
- 社会福祉法人名古屋ライトハウス
- 所在地
- 愛知県名古屋市昭和区川名本町1丁目2番地
- URL
- https://nagoya-lighthouse.jp/
- 事業内容
- ・障害者支援施設
・特別養護老人ホーム
・盲養護老人ホーム
・障害福祉サービス事業
・一般相談支援事業・特定相談支援事業
・障害児相談支援事業・障害児通所支援事業
・地域活動支援センター
・移動支援事業
・福祉ホーム
・老人デイサービス事業・老人短期入所事業