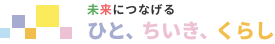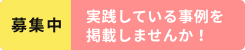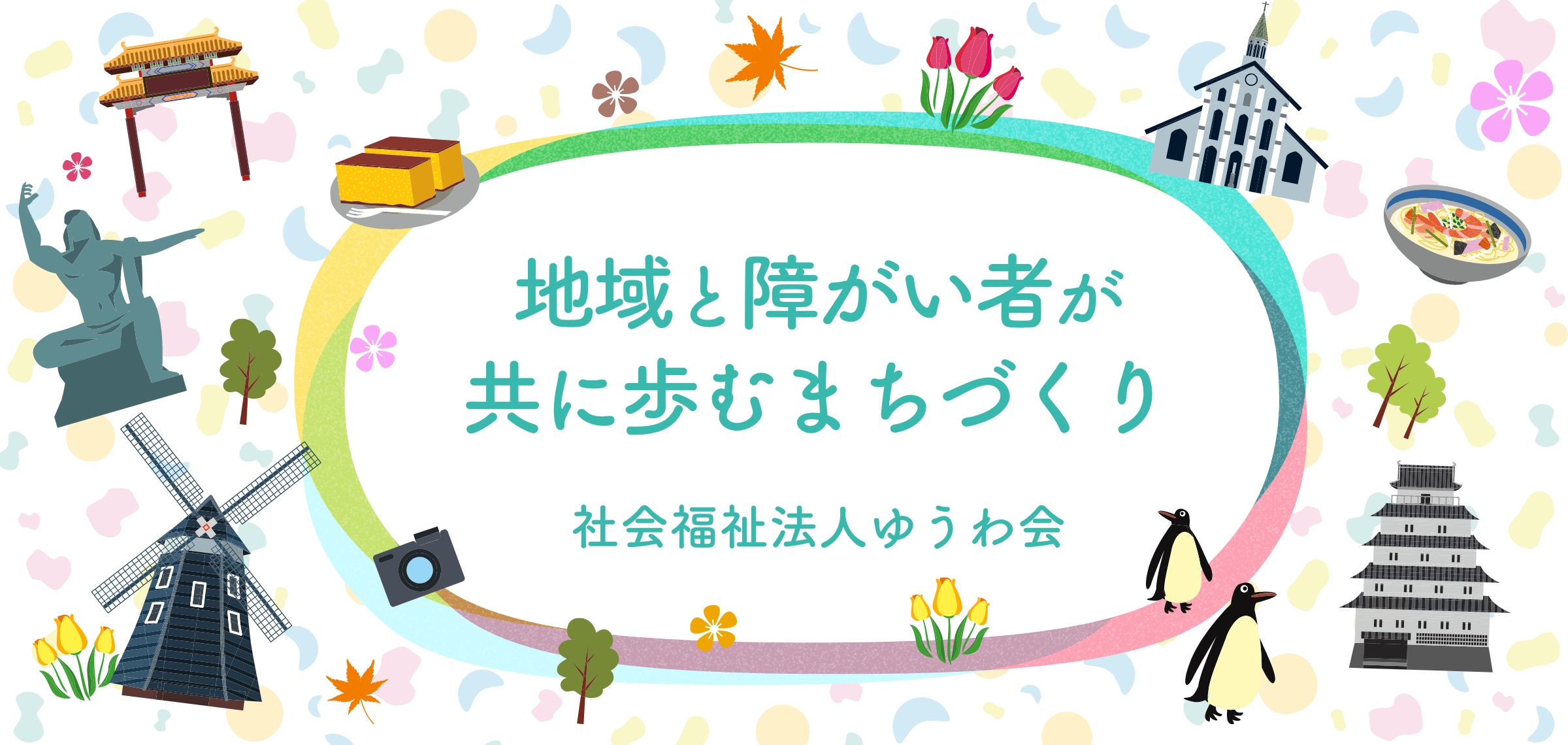障がい者が安心して暮らせるまちづくり
——これは国全体の目標であり、行政とも協力しながら進めていくべき課題です。しかし、実際にそれを地域レベルで推進するには、多くの壁が立ちはだかります。障がい者施設の移転計画が地域住民の反対にあったり、障がい者に対する誤解が根強く残っていたりする現状の中で、ゆうわ会はどのように地域の人々と向き合い、信頼関係を築いているのでしょうか。長崎市西山地区を拠点とするゆうわ会の取り組みと、地域共生社会を実現するための挑戦を紹介します。

地域の偏見を乗り越えて
長崎市西山地区に拠点を構えるゆうわ会は、障がい者支援のための施設運営を行ってきました。しかし、障がい者施設の新設や移転の際には、地域住民の理解を得ることが難しい場面が何度もありました。
例えば、ゆうわ会が新たな障がい者支援施設を計画し、現在の拠点から20分ほど離れた地区に移転しようとした際、自治会との協議で施設移転が了承されたものの、その地域の住民から強い反対の声が上がりました。「施設ができると地域の治安が悪化するのではないか」「障がい者がうろうろするのが怖い」といった、根拠のない偏見が根強く残っていたのです。
このような地域の反発を受け、移転計画は1年以上延期されました。最終的には、より地域住民の理解が得られる場所を選び、自治会と協議を重ねた上で移転を決定しました。こうした課題に直面しながらも、ゆうわ会は地域との信頼関係を築くために努力を続けています。
また、長崎市は歴史的にも外部からの文化や人を受け入れてきた土地ですが、地域ごとの結びつきが強いがゆえに、新しいものを受け入れることに慎重な面もあります。この地域特有の課題を乗り越え、障がい者施設が自然に受け入れられるようになるためには、地域の住民と障がい者が日常的に触れ合い、互いに理解し合う機会を増やすことが不可欠です。
交流を通じた理解の促進
障がい者に対する偏見の多くは、「知らないこと」から生まれます。そこで、ゆうわ会は地域住民との交流を積極的に進めるために、以下のような取り組みを行っています。
西山ふれあい祭り
西山ふれあい祭りは、毎年秋に開催される地域交流イベントです。障がい者支援施設の利用者、職員、地域住民が一堂に会し、模擬店やステージイベントを通じて親睦を深める機会を提供しています。特に、地域の小学生による合唱やダンスパフォーマンスは、障がい者と子どもたちが自然な形で交流するきっかけとなっています。
ある年の祭りでは、施設利用者が作った焼き菓子や手工芸品が地域の住民に大変好評で、販売開始からわずか1時間で完売しました。販売を通じて、障がい者が地域社会の一員として貢献できることを示すことができました。ある地域住民は、「施設の方々がこんなに素晴らしいものを作っているとは知りませんでした。これからも応援したいです」と話していました。


スマイリーデイ
スマイリーデイは、保育園児と障がい者が定期的に交流するプログラムです。障がい者施設の利用者が地域の保育園を訪問し、子どもたちと一緒に遊んだり、簡単な作業を体験したりします。
ある回では、施設利用者と園児が一緒に折り紙を折るワークショップが行われました。最初は緊張していた子どもたちも、障がい者の方々が優しく折り方を教えてくれるうちに、笑顔が増えていきました。「また一緒に遊びたい!」と話す子どもたちの声に、施設利用者も目を輝かせていました。

地域避難所としての活用
災害時には、施設を福祉避難所として地域住民に開放しています。特に長崎市は台風や豪雨の影響を受けやすい地域であり、避難所の役割は重要です。これにより、地域住民が障がい者と共に避難する経験を積み、互いの理解が深まるきっかけにもなっています。
ある年の台風時、施設に避難してきた地域の高齢者が「施設の利用者さんが親切に声をかけてくれて、とても安心しました」と語ったことが印象的でした。

スポーツ活動の推進
スポーツを通じた交流も積極的に進めています。知的障がい者のためのサッカーチームは、地域のクラブと合同で練習を行い、一般の試合にも参加するようになりました。最初はぎこちなかった地域のプレーヤーも、次第に障がい者の個性や能力を理解し、自然な形でチームワークを築いていく様子が見られました。
ある試合では、施設利用者がゴールを決めた瞬間、会場全体が大きな歓声に包まれました。「みんなで一緒にプレーする楽しさを知った」と語る選手の笑顔が、交流の意義を物語っていました。

人材採用と定着のための取り組み
障がい者支援において、支える側の人材の確保と定着も重要です。ゆうわ会では、地域住民や若手人材を積極的に巻き込み、長期的な支援体制を築いています。
こうした取り組みにより、地域住民の意識が変化し、障がい者支援がより広がる環境を整えています。
-
- 地域ボランティアの参加促進
- イベントや日常活動に地域の人々が関わる機会を増やし、障がい者との自然な関係を育む。
-
- 福祉系大学や専門学校との連携
- 学生向けの体験実習やインターンシップを提供し、福祉の現場を学ぶ機会を拡充。
-
- 職員研修の充実
- 定期的なスキルアップ研修を実施し、職員のモチベーション向上と定着を図る。
-
- スポーツやレクリエーションを活用した職場環境づくり
- 職員が障がい者とともに活動する機会を増やし、職場の一体感を醸成する。


障がい者の働く場を広げる
障がい者が地域で安心して暮らすためには、働く場の確保が重要な要素となります。ゆうわ会では、障がい者が能力を活かして働ける環境を整え、地域とのつながりを深めるための就労支援を展開しています。
ながさきワークビレッジ
- 業態名
- 就労継続支援B型事業所
- 目的
- 障がい者が働く機会を得て、自立を目指す
- 活動内容
- • 地元農家との提携による農業体験
• パンや菓子の製造・販売
• 繊維製品や手工芸品の制作 - 成果
- 利用者の定着率向上、地域住民の利用増加

農業体験では、利用者が地元農家と協力し、野菜の収穫や栽培を行っています。農作業を通じて、規則正しい生活習慣を身につけるとともに、地域住民と触れ合う機会を増やしています。また、パンや菓子の製造販売においては、施設内の工房で利用者が製造工程に携わり、販売を通じて接客スキルを習得。これにより、社会性を養い、自信を持って働ける環境を提供しています。
チャレンジド・ショップはあと屋
- 業態名
- 障がい者の自主製品販売店
- 目的
- 障がい者の手作り製品の販売を通じた社会参加
- 活動内容
- •商店街に出店し、利用者が接客を担当
•地域住民との交流イベントを開催 - 成果
- 販売利益の向上、地域住民との相互理解の促進

チャレンジド・ショップはあと屋では、障がい者が手作りした雑貨や食品を販売し、地域住民との交流を深めています。接客業務を担当することで、利用者は社会との接点を持ち、仕事への責任感を培っています。また、地域住民が商品を購入することで、障がい者の働く姿を直接見る機会が増え、地域の理解促進にもつながっています。
ある年、地域の夏祭りにゆうわ会の利用者たちが参加し、手作りの小物や食品を販売するブースを出展しました。初めは地域住民も遠巻きに見ているだけでしたが、利用者たちの明るい呼びかけや笑顔に触れるうちに、多くの人々がブースを訪れるようになりました。特に、利用者が心を込めて作った焼き菓子は大好評で、完売するほどでした。この経験を通じて、地域住民は障がい者の能力や人柄に触れ、理解を深めるきっかけとなりました。
これらの交流活動の結果、地域住民の障がい者に対する理解が深まり、施設への訪問者数も増加しました。また、地域からのボランティア参加者も増え、障がい者と地域住民が共に活動する機会が増加しました。さらに、地域の学校からの依頼で、障がい者理解のための講演やワークショップを行うなど、地域全体での共生意識の向上が見られました。
企業連携型インターンシップ
- 業態名
- 一般企業と協力した職場実習
- 目的
- 障がい者の実務経験の向上と一般就労への移行
- 活動内容
- •地元企業との提携による短期インターンの実施
•企業向けの障がい者雇用研修の実施 - 成果
- 障がい者の一般就労率の向上、企業側の受け入れ意識向上

地元企業と連携し、障がい者が実際の職場環境で働く機会を提供。これにより、一般就労に向けたステップアップを図るとともに、企業側の理解を深めることを目的としています。インターンシップ参加後、多くの利用者が企業から正式採用され、一般就労へと移行しています。
このように、ゆうわ会では多様な働く場を提供し、障がい者の社会参加を支援しています。地域との協力を深めながら、今後もさらなる就労支援の拡充を図っていきます。
未来への挑戦と次世代へのつなぎ
ゆうわ会は、地域共生社会の実現に向けて、継続的な取り組みを進めています。
- 障がい者スポーツの普及
- 地域のサッカークラブやテニスチームと連携し、障がい者がスポーツを通じて社会参加できる機会を拡大。
- 地域との継続的な対話
- 障がい者施設の運営や新たなプログラムに関して、地域住民と定期的な意見交換を行い、相互理解を深める。
- 職員のスキル向上
- 障がい者支援の質を向上させるため、職員向けの専門研修を強化し、福祉人材の育成に努める。
こうした取り組みにより、職員の定着率は向上し、地域福祉の担い手として成長する機会が広がっています。 地域と共に歩み、誰もが安心して暮らせるまちづくりを目指して、ゆうわ会の挑戦は続きます。
施設概要
社会福祉法人ゆうわ会は、長崎の地で代々カトリック信仰を守りながら、社会福祉の実現に努めてきました。理念は「谷間に光を共に生きる」。昭和41年に「さくら保育園」を開園し、待機児童問題に対応するために新たな保育園を開設。その後、知的障がい児が社会に居場所を見つけられないことを知り、障がいのある人たちと地域社会の共生を目指して「竹内学園」を開設しました。現在、社会福祉法人ゆうわ会は、障がい者支援事業や保育事業を展開。障がいのある方と地域住民が互いに理解し、支え合う社会の実現を目指し、スポーツ活動やイベントを通じた地域交流を積極的に推進しています。

- 法人名
- 社会福祉法人ゆうわ会
- 所在地
- 長崎市西山4丁目610番地
- URL
- https://www.yuuwakai.or.jp/
- 事業内容
- ●障がい者支援施設の経営
●保育所の経営
●障がい福祉サービス事業の経営
●相談支援事業の経営
●域生活支援事業の経営
●就労支援事業の経営