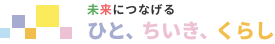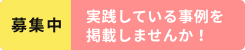“おせっかい日本一”を掲げるまち、八尾市で
大阪府八尾市は、第4次地域福祉計画の中で、「おせっかい日本一」を掲げています。その背景にあるのは、地域全体で声をかけ合い、困っている人に手を差し伸べる文化。八尾隣保館は、専門職として福祉を提供しながら、こうした地域の力と協力しながら、ともに地域を支え続けてきました。なかでも2021年に立ち上がった「地域支援事業なないろ」では、地域のための多様な取組を実施し、活動の場を広げています。

地域支援事業なないろ
誕生
地域福祉の最前線で活動を続けてきた八尾隣保館でしたが、コロナ禍によって“地域とのつながりの希薄化”に直面。荒井惠一理事長は、全職員にあてた手紙のなかで、「地域との再接続」を呼びかけました。
職員たちは地域のための取組強化に立ち上がりました。生活困窮者へのレスキュー事業をはじめ、20年以上前から地域のための取組を続けてきましたが、既存の実践を組織的に束ね、より安定的な支援が継続できるよう、改めて「地域支援事業」として再構築しようと「地域支援事業なないろ」が生まれました。
由来
名称は職員から公募し、その中で「なないろ」が採用されました。今まで実施していた多様な事業を7つに再整理し、「見えづらかった支援を整理し、外部にもわかりやすく伝える」意図が込められています。
活動
なないろでは地域ニーズを踏まえ、以下の7つの取組を軸に活動をしています。
・活動1. 生活困窮者レスキュー事業+スマイルサポーター事業
・活動2. 中間的就労
・活動3. 法人後見事業
・活動4. 住宅確保要配慮者居住支援法人
・活動5. 食支援活動
・活動6. 子どもの見守り強化事業
・活動7. 大阪DWAT

地域の最前線で生活を支える
生活困窮者レスキュー事業+スマイルサポーター事業
生活困窮者レスキュー事業では「今日食べるものがない」そんな切迫した状況にある生計困難者に向けて、食料等の現物給付型の経済的援助を実施。スマイルサポーター事業では、養成講座を修了した保育士等が、生活困窮等をはじめとしたさまざまな課題を抱える人々へ、ワンストップの総合生活相談を実施しています。
本事業は、制度の狭間で困る人が出ないよう、対象者は高齢者、障がい者、子どものいる家庭など特定の分野ごとに絞ることなく、地域のセーフティネットとして機能するようにしています。


その人に合った仕事をつくる
中間的就労
中間的就労では、働くことに不安を抱える方に寄り添いながら、その人らしく働くことへの道筋をていねいにつくっています。
八尾隣保館では、地域の社会福祉協議会と連携しながら、コーディネーターとして支援体制を整備し、施設内での受入れを実践しています。
ご利用者は成功体験を積み重ねることで、一般就労に移行するケースも多く、“社会的リハビリ”としての役割を果たしています。


深刻な担い手不足に挑む
法人後見事業
認知症や障がいなどにより判断能力が不十分な人を支援する制度が成年後見制度です。これまでは弁護士や司法書士、社会福祉士といった専門職が個人として後見人に就くことが一般的でしたが、近年、その担い手不足が深刻な課題となっています。
そこで大阪府は、社会福祉法人自らが後見人になる法人後見の仕組みづくりを進めています。八尾隣保館は、本事業における府内第1号の法人後見人を受任しました。


入居後も支援を続ける
住宅確保要配慮者居住支援法人
福祉的な困難を抱える人々が、居住先を見つけること、賃貸契約を結ぶことに困難が伴う事例は珍しくありません。国土交通省が2017年から制度化した、住宅確保要配慮者居住支援法人は、こうした背景のもとで誕生した取組です。
八尾隣保館も2018年に本取組に参画。住まい探しの支援だけでなく、入居後のトラブル対応や見守り、さらには亡くなった後の残置物処理の支援まで、多面的なサポートを提供しています。
さらに、2025年4月には、八尾市と社会福祉協議会、複数の福祉法人などで構成される「八尾市居住支援協議会」も発足し、地域全体での連携が強化。単に住む場所を提供するのではなく、住み続けられる環境を地域ぐるみで支え続けることを大切にしています。


多面的支援で子ども食堂をサポート
食支援活動
八尾隣保館が展開する食支援活動は、地域の子ども食堂の活動を支える取組です。背景には、子ども食堂の運営主体と支援したい団体や個人間の、支援のつなぎ手の不在という課題がありました。そこで、八尾隣保館では、地域の子ども食堂に食材を届ける中間支援の役割を担うように。具体的には、八尾市域及び周辺の子ども食堂25か所ほどに食品を分配しています。
さらに支援のなかで見えてきた、食支援以外の子ども食堂運営における課題にも目を向け、取組を広げています。たとえば助成金申請のサポートやボランティア希望者とのマッチングなどの活動です。八尾隣保館では、それぞれの子ども食堂が抱える問題に対し、福祉の専門性を活かした支援を柔軟に行っています。


見えづらい家庭の問題に寄り添う
子どもの見守り強化事業
子ども家庭庁の制度で、八尾市からの委託事業として、子どもの見守り強化事業(正式名称:要支援児童等見守り強化事業)を実施。困難を抱え、見守りが必要とされる子どもや家庭に対し、行政と連携しながら支援の手を差し伸べる取組です。「家庭へのアウトリーチ」「食材の提供」「子どもの居場所づくり」の3つを事業の柱にしています。
行政の支援が届きにくい家庭に対し、八尾隣保館の職員が食材を持って訪問し、「困っていることはありませんか?」と声かけをすることで、家庭で抱え込んでいた問題が明らかになり、その後の支援に繋がるケースも多くあります。


非常時も福祉的支援を絶やさない
大阪DWAT
「大阪DWAT(災害派遣福祉チーム)」は、大阪府の主導により組織されており、八尾隣保館もその活動に参画しています。 令和6年に発生した能登半島地震では、大阪DWATが初めて実働派遣を実施しました。この派遣には、過去に災害現場での支援活動を経験した八尾隣保館の職員も参加し、その経験を活かして現地での支援に尽力しました。
活動内容としては、一般の避難所では生活が困難な高齢者や障がい者などを対象に、一時的に滞在可能な1.5次避難所から、より適した2次避難先(ホテルや福祉施設など)への移動を支援しました。この際、「どのような支援が必要か」「どんな環境であれば安心して過ごせるか」といった一人ひとりの状況に寄り添う、福祉の専門的視点に基づいたマッチングもDWATの重要な役割です。
実働派遣を経験したことで、「次はぜひ自分も参加したい」との声が職員の間で広がり、当初4名だった大阪DWATへの登録者は、現在では11名に増えています。

施設概要

- 法人名
- 社会福祉法人 八尾隣保館
- 所在地
- 大阪府八尾市南本町3丁目4番5号
- 理事長
- 荒井 惠一
- URL
- https://yaorinpokan.or.jp/
- 事業内容
- ・認定こども園(2ヵ所)
・母子生活支援施設
・特別養護老人ホーム
・養護老人ホーム
・地域包括支援センター(2ヵ所)
・デイサービスセンター(高齢3ヵ所・障害1ヵ所)
・ショートステイサービス(高齢2ヵ所・障害1ヵ所・児童1ヵ所)
・ホームヘルプサービス
・ケアプランセンター(2ヵ所)
・サービス付き高齢者向け住宅
・学童保育 - 法人理念
-
一、信頼
私たちは利用者に信頼されるよう努めます。
私たちは地域に信頼されるよう努めます。
私たちは社会に信頼されるよう努めます。一、創造
私たちは信頼を創造します。
私たちは安心と安全を創造します。
私たちは改善と新たな事業を創造します。一、貢献
私たちは利用者の自立支援に貢献します。
私たちは地域に貢献します。
私たちは社会に貢献します。